
1 相談の概要
相談に来られた方は、病院・事業所の食堂運営等を営んでいるA社の代表者でした。
A社は、税金の滞納により税務署から差押えを受けたことにより、急激に資金繰りが悪化し、金融機関だけではなく、多数の食材の仕入先業者に対する支払いも滞納し、社員の給料も遅れている状況でした。
A社は、月末には資金が底を尽き、事業の継続ができなくなるため、事業の継続及び従業員の雇用を守れないかということで相談に来られました。
2 事業再生の方法
2-1 私的整理
債権者との合意により、債務の支払いの猶予や免除を求めていく方法です。
A社の場合、金融機関だけでなく、多数の食材業者に対しても支払いを滞納をしている状況でした。
多数の債権と話し合いで解決するには、時間的余裕がない状況でしたし、債権者との合意ができる目処もありませんでした。
私的整理という手段をとることができる状況にはありませんでした。
2-2 民事再生
裁判所に民事再生の申立てして、申立前に発生している債務を一度棚上げして、裁判所が関与する法的手続により、事業の再生を図る手法です。
月末に資金が底をつくのであれば、民事再生の申立てをして、債務の支払いを一度止めるということも考えられますが、民事再生の申立てをするには、裁判所に納付する予納金として数百万円が必要です。
A社には、裁判所に納付する予納金を準備できような資金的な余裕はなく、民事再生の申立てもできない状況でした。
2-3 事業譲渡+破産
いきなり破産をしたのでは、病院・事業所の食堂運営等が止まり社会的影響も予想されました。
そこで、支援先X社に事業譲渡をして、X社への事業承継が確認ができたところで破産をする方法を選択しました。
ただし、事業譲渡に伴いX社へ転籍する社員は、事業譲渡の時点ではA社からの給料が未払いのままであり、未払給料については、事業譲渡後、A社が売掛金を回収して支払う予定でした。
しかしながら、売掛金の入金を待っている間に、売掛金が差し押さえられたりして、A社が確実に回収できる保証はどこもありません。
そこで、支援先Xに、A社の売掛金も買い取ってもらい、すぐに現金化し、従業員に対する給料をすべて支払いをして、事業継続を可能としました。
また、事業譲渡実行前には、弁護士同席の下、従業員に対し説明会を実施しました。重要な取引先には弁護士が同行し、事業継続の協力を要請しました。
これらの対応により、A社の事業及び従業員の雇用はX社に承継され、その後、A社は破産の申立てをしました。
2-4 まとめ
最終的に会社が破産することになったとしても、破産をする前に、事業譲渡をすることにより、経営者がこれまで築いてきた事業や従業員の雇用を守ることができます。
これも事業再生の一つの手段です。
会社にお金がない、時間がないとすぐに諦めるのではなく、最後まで諦めないことが肝要です。
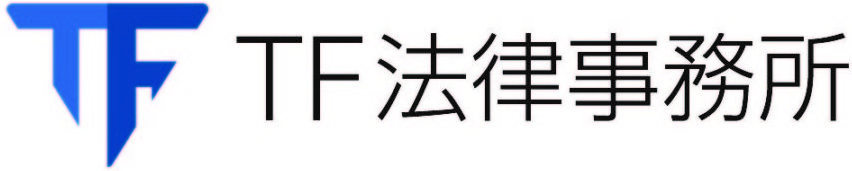
コメント